聞きたかったメンタルヘルスの話 vol.24
このコラムは筆者が以前某医療コラムで連載していた修正前の記事本文です。内容は作成当時のもので、現在は異なることもありますので、ご了承下さい。あくまでアーカイブとしてご覧ください。
精神保健福祉の現場では精神疾患患者の回復の一助として「ピア・カウンセリング」やピア・スタッフによる「ピア・サポート」がおこなわれています。「ピア」というのは英語のpeerで直訳すると「同等・同格の人」「仲間」となります。この場合では「同じような経験をしている仲間=当事者」という意味で使われています。私自身、ピア・スタッフとしてピア・サポートをしております。
「ピア・カウンセリング」は癌(がん)患者同士でも行われたりしますが、精神保健福祉では精神疾患を持った同士でお互いの自立活動のためにおこなわれます。同じような症状、同じような副作用、同じような生きづらさを経験してる同士こそ分かり合える「会話」が一定のルールのもと安心して話すことができるのが特徴です。そこに体験者としての問題の解決例を聞くことであったり、問題との向き合い方を学んだり、自分の言葉にできなかったモヤモヤした思いを言語化できる機会でもあります。
「カウンセリング」というと、分析や助言・指導をもらうことを想像しがちですが、ピア・カウンセリングは有資格者のおこなうカウンセリングとは違い、主に自分の発言と傾聴による共有、不安の軽減、そして新しい気づきを得られることを主に目的としています。僕も「ピア・カウンセラー」としても活動していますが、たまにそれを知らない方に勘違いされ「有資格者のカウンセラー」と思われることもあり、カウンセリングをしてもらいと言われることもあり、誤解のないよう「ピア・サポーター」と名乗るようにしました。
また「ピア・カウンセリング」には一対一でおこなうものと、グループで行われるものがあります。先ほどの一定のルールというのは主にグループででおこなうもので決められています。それでは「一定のルール」とはどんなものでしょう。
まずは対等であることの分かち合いです。お互いの存在を脅かすようなことはあってはなりません。発言内容も誰か個人を攻撃、誹謗・中傷、批判するような内容は話してはいけません。そして、その発言に対しても批判、批評、否定することはNGです。反応はうなずきなどで返します。安心して話ができる場のためのルールです。また時間も対等です。1人の人が長く話しすぎたりしないようにします。人の話に割り込むこともしてはいけません。
また、宗教や政治のはなし(特に勧誘など)、アダルトや性的な話をしないなどのルールもあります。セクシャリティや男性ならでは、女性ならではの悩みもあるので、性別を限っておこなわれるグループ・ピア・カウンセリングもあります。
言いっ放し、聞きっぱなしの場であることも重要なルールです。その場で話されたことは他の場で蒸し返したりしない約束です。安心して悩みを話すことができるためです。
また言いたくないことは言わなくてもOKです。
これらのルールを保持するため、進行役やタイムキーパーがいる場合もあります。
それでは一対一のピア・カウンセリングの場合はどうでしょうか。主に電話相談などがあります。片方が相談し、もう片方が聞き役となります。どちらも当事者というのが特徴です。聞き役は“傾聴”が基本です。そしてどんな気持ちであったか“聞き出す”テクニックを用いる場合もあります。ただし、基本聞き役もアマチュアです。共感や知っている情報の提供、自分の場合の話を返すのが限度です。専門的な相談はできかねます。また聞く方も疲れます。時間は1回20分が区切りと思ってください。
話の相談ていうのは「がっつり聞き出してもらいたい」という場合と、「聞いてもらうだけでいいから」という場合や具体的な解決例を聞きたいなど、そのニーズは様々です。またピア・カウンセラーのあり方も様々です。そこは理解しておいてください。
それでも、当事者の共感を得られることの安心感は大きく、ピア・カウンセリングの効果はある程度あると思います。それで“救い”をえられることもあります。
グループ・ピア・カウンセリングは自助グループ(セルフヘルプ・グループ)や地域活動支援センターなどの場でプログラムの一環としておこなわれることが多いです。一対一は同じく地域活動支援センターの中でおこなわれるか、電話相談の一部でおこなわれています。
そんな地域活動支援センターや就労継続支援事業所などでピア・サポートをしているのが「ピア・スタッフ」です。定義は「当事者」というだけです。ボランティアの方もいれば、給与をもらうピア・スタッフもいます。どちらにも守秘義務などはあります。
全国でもピア・スタッフは増え続けているようです。しかしピア・スタッフがする職務内容は様々です。ピア・カウンセリングを主に運営する人もいれば、福祉の専門的な支援の一員として活躍している人もいます。
ピアとしての役割というのも「これだ」というものはありません。僕が思うのは「支援の一員」でいることそのことが大事だと思っています。そこにある当事者としての気づきが何らかの形で支援に活かされればいいと思っています。その活かされ方も様々だと思います。
また「ピア・スタッフになりたい!」という声も多く聞かれます。実は一般に募集されることはまだ少なく、「一本釣り」と呼ばれる直接の誘いが多いのが実情です。そう言ったピア・スタッフの募集のあり方や労働条件などを一緒に考えようと「日本ピアスタッフ協会」が活動しています。http://peersociety.jimdo.com
また千葉県では都道府県では初めて「ピアサポート専門員」養成講座を開いており、修了した方には「修了証」を県知事の名で発行されます。
このように「ピア」という当事者の自助というのは現在とても注目されており、ピア・サポートも数々の研究が始まっています。
ひとりで悩んでいて相談に困っている場合は「ピア・カウンセリング」から入るのも選択肢のうちの一つです。

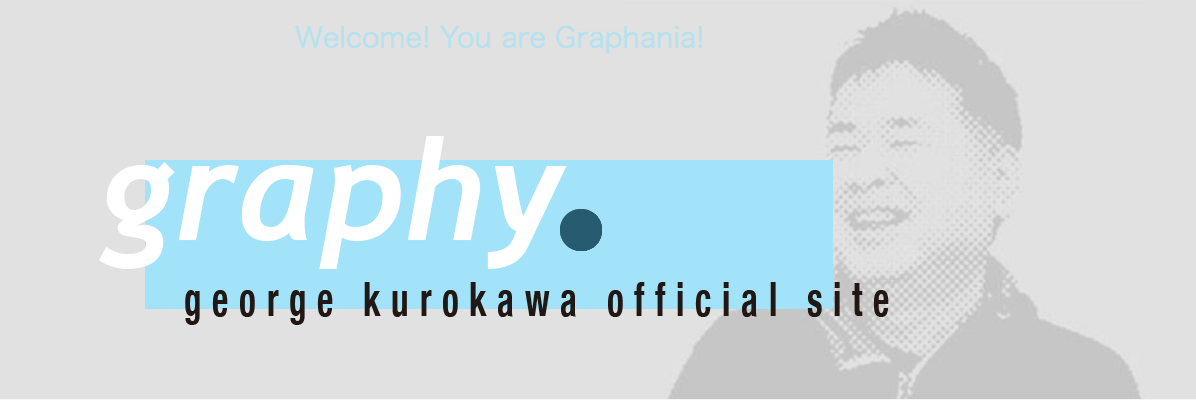

コメント