聞きたかったメンタルヘルスの話 vol.18
このコラムは筆者が以前某医療コラムで連載していた修正前の記事本文です。内容は作成当時のもので、現在は異なることもありますので、ご了承下さい。あくまでアーカイブとしてご覧ください。
精神疾患患者の中では、「精神疾患は完治する」と言う人や、「一生薬を飲み続けなきゃいけないんだよ。」と言う人もいます。また回復するために薬物療法以外にカウンセリングなどによる精神療法や微電流で刺激を与える電気治療、認知行動療法や作業療法などがあります。WRAPやピア・カウンセリング、当事者研究など補助的なものもあります。いずれにしても、「合う」「合わない」がタイミングや相性で出てきます。うまくマッチングすれば効果的でしょう。ではそれらを続けていくとどうなるのでしょうか。
「完治」「全治」「治癒」
完全に治ることです。精神疾患の場合、早期発見、早期治療した場合、疾気を患う前の状態に治る可能性はあります。薬も飲まず、生活に気をつけながら、元の生活を取り戻すことができます。生活に気をつけながらというのは、「再発」を防ぐためです。
「寛解」
一般的には症状が落ち着き、生活にも問題がない状態を指します。精神疾患患者の中では定義にいろいろな意見がありますが、多くは「薬を飲まなくてもいい状態」を指していることが多いです。症状が落ち着いた方は、薬も必要な時だけ頓服として飲むなど、安定している状態です。また、薬を飲み続けていても、服用さえしていれば生活に不便がない状態であれば、それを「寛解」と呼ぶ方もいます。
「リカバリー」
最近よく耳にする言葉です。英語の直やでは「回復」を指します。精神疾患患者や支援者の中では、主体的に自分の人生を歩むことで自己実現することやそれを目指すことを指します。精神疾患における「リハビリテーション」も同義をなすことがあります。
ただし、リカバリーにおいても何をゴールとして定義するには多数の意見があります。社会的に復帰すること、就職すること、寛解になること、自分らしく生きること…と様々です。
…では、以前のコラムで書いた長期入院されている患者さんはどうでしょう。
長期入院患者の多くは病状は安定しているのです。ただし、退院した後に行く場所やその支援がないために余儀なく入院されているのが実態です。そして、きっと多くの入院患者さんが主体的でない人生を送っていることだと思います。そこには残念ながら「リカバリー」の視点はありません。
ここで「回復」へのプログラムの幾つかをご紹介します。
OT(occupational Therapy)
OTは作業活動を中心に機能の回復を目指す作業療法です。座学のようなものもあれば、ゲームのようなものもあり、また軽作業もあります。季節ごとのプログラムや軽運動もあります。作業療法士がついて行われます。
デイケア・ナイトケア
作業療法や生活に必要な技術を学ぶプログラム(料理、PCなど)、リクリエーション(スポーツ、カラオケ、散策など)、食事会などをグループで行います。これを利用することにより日中活動を規則正しく保つことができます。
ピア・カウンセリング(Peer Counseling)
ピア・カウンセリングは当事者同士の小グループで一定のルールのもと話をすることです。ピア(Peer)とは仲間、立場が対等な人という意味があります。一定のルールとは主に発言を脅かさない、その場で話されたことを他言しないなどがあります。僕自身がピア・カウンセリングを学び、ピア・カウンセラーとして働いております。ここでピア・カウンセラーが「カウンセリング」をするという誤解がよく生じます。ピア・カウンセリングもピア・カウンセラーも、参加者に気づきを持ってもらえることや、参加者が自分の気持ちを話しをして一時的に共有されることで安心感を得られることにが特徴です。一般のカウンセラーが行うカウンセリングとは違います。
WRAP(Wellness Recovery Action Plan)
日本語訳では「元気回復行動プラン」と言います。自分が元気になることを探し、プログラムの中には「元気に役立つ道具箱」を作り、体調を崩すサインへの気づきや対処策をまとめることもあります。WRAPファシリテーターが進行します。これはあくまで個人的な感想ですが、内容が直訳されているようなこともあり、今後もう少しローカライズされた方がよくなると思っています。WRAPに参加して「元気になった」という声もあれば、「疲れた」という声もたまに耳にすることもあります。
ピア・カウンセリングもWRAPも進行役が参加者に対してどれだけ気を配れるか、どれだけ参加者の状態を把握できるか、どれだけ言葉を紡ぎ出せるかが鍵になります。有効に働けば、回復の一助となりますが、参加者の体調や進行役の無配慮、またタイミングなどにより体調を崩す場合があります。
農業
土いじりや、植物を育てること、朝早く起きることなど、いろいろな要素があり、農業に携わることで回復される方もいます。農園運営などを療法の一つとして行っているところがあります。
僕は、希望の種や言葉を持つことが回復へのきっかけとなると思っています。そこに欲や希望、憧れが出てきて、それを自己実現するために何が必要なのかを探し始め、気付いたら休みながらもそれに取り組んでいたというのが人生における回復だと思っています。私の著書「焦らない, でも諦めない.」はそんな思いからつけたタイトルでした。

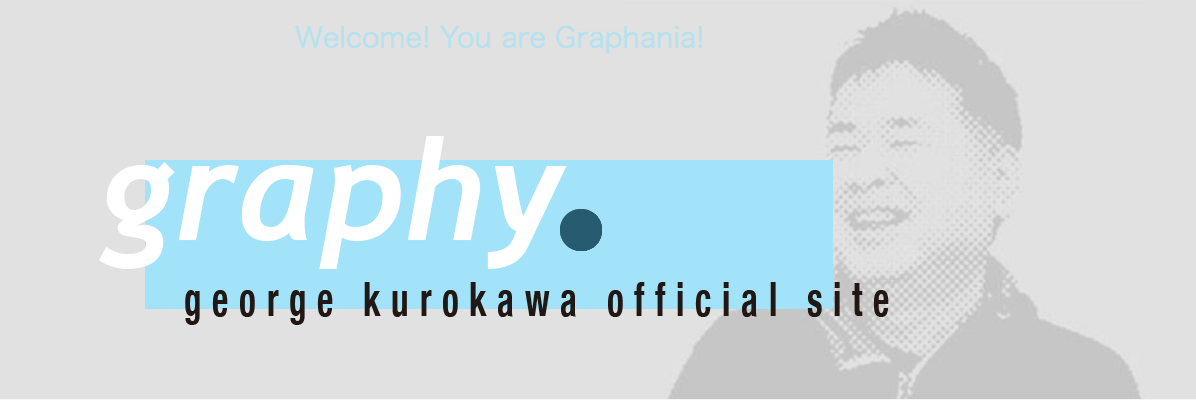

コメント