聞きたかったメンタルヘルスの話 vol.17
このコラムは筆者が以前某医療コラムで連載していた修正前の記事本文です。内容は作成当時のもので、現在は異なることもありますので、ご了承下さい。あくまでアーカイブとしてご覧ください。
精神疾患の症状にもいろいろなものがあります。今回は「症状」に焦点を当ててお話ししたいと思います。
「うつ」ー負の感情ー
精神疾患でよく見受けられる「うつ」と言う症状。気持ちもふさぎこみ、やる気が出ない状態です。ネガティブな思考が連鎖し、落ち込み続けることもあります。「自分が全部悪いんだ」「生きている意味がない」など自責の念も出ます。夢や希望も抱けなく、憂うつな気分が続きます。感情や思考が希薄になり、集中力も落ちます。今まで好きだったものにも関心が薄れ、テレビや映画を見ても楽しくなかったりします。ネガティブな考えが出ます。僕自身はネガティブな思考が止まらず、連鎖する状態になったことがあります。
「うつ状態」と「うつ病」と「躁うつ病」
この「うつ」の症状が起きていることを「うつ状態」と言いますが、必ずしも「うつ病」であるとは限りません。この「うつ状態」を起こす疾患としては、「躁うつ病(双極性障害)」「統合失調症」「発達障害(自閉症、アスペルガー症候群)」「発達障害(ADHD 注意欠如多動性障害)」「てんかん」「パニック障害」「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」「パーソナリティ障害」「強迫性障害」など別の精神疾患であることがあります。違法薬物の使用で現れることもあります。
精神疾患以外でも、「睡眠無呼吸症候群」「関節リウマチ」「ビタミン欠乏症」「脳血管障害」「認知症」「パーキンソン病」「甲状腺機能低下症」「心筋梗塞」「慢性閉塞性肺疾患」「全身性エリテマトーデス」など「うつ状態」が現れる疾患が多々あります。また癌などの大病になった時のショックとして、「うつ状態」になることがあります。
「うつ病」で処方される薬は「うつ病」には効果が見られますが、他の疾患では効果が出なかったり、悪化する場合もあります。
うつ病の典型的な症状として、不眠、食欲低下が起こります。
他の疾患のうつに伴う症状としては、過眠などがあります。産後うつなどはホルモンのバランスの変化により起こります。治療には専門医との相談と周囲の理解が不可欠です。放置しておくと「うつ病」へと変化する場合があります。
「そう状態」
うつ状態と相反する状態です。いわゆる「ハイ(high)」な状態で、ケラケラ大声で笑い続けたり、興奮し続けたりします。怒りとして出る方もいます。多弁になり、抑圧的な言動をする場合もあります。じっとしていることができません。活動的になることで「回復した」と誤解する場合があります。「そう状態」も「躁うつ病(双極性障害)」だけでなく、「統合失調症」や違法薬物の使用で出てくることがあります。「肺炎」「梅毒」などで進行麻痺を起こし、「そう状態」になることもあります。食欲や性欲は上がります。過活動により対人関係で問題が起きることが増えます。
「妄想」
現実には起きていないこと、起きないことが実際にあるかのように強く確信を持ち、それがどんどん膨らみます。誰が否定してもその確信が訂正でいない状態です。症状が起きている当事者にはそのストーリーは自然なものなのですが、他の人からは矛盾点も多く理解ができません。「テレビに見られている」「自分の考えていることが組織に伝わっている」「誰かに追跡されている」「影で噂されている」「嫌がらせを受けている」などの訴えもあります。「電波が届く」「自分は神だ」のような発言も見受けられます。統合失調症に多く見られます。その他、「うつ病」や「躁うつ病」「認知症」でも見られ、妄想性の障害(疾患)の場合もあります。
「幻覚」「幻聴」「幻視」「幻臭」
実際にないものがそう見えてしまったり、声が聞こえてしまったり、臭ってしまったりする症状です。僕自身は疲れた時や朝起き抜けの時に玄関のチャイムが鳴ったように聞こえる「幻聴」がよくあります。人の声の「幻聴」の訴えが一番多く聞かれます。中には「幻聴」に支持されることもあるようです。北海道・浦河にある「べてるの家」が主催で行われる「べてるまつり」では「幻聴&妄想大会」というものがあり、それぞれの幻覚と向き合うことを共有しています。「幻聴さん」と呼んで幻覚との付き合い方を工夫しています。幻聴は抑圧的な声であったり、本人を混乱される声が多かったりしますが、付き合い方次第で「幻聴さん」は「不調のサイン」や味方になってくれる幻聴に変えていくこともできるようです。「べてるの家」で行っている「当事者研究」もとても勉強になります。
「引きこもり」
周りとのコミュニケーションを遮断してしまう状態です。自分の部屋に閉じこもってしまうのが一番多いでしょうか。厚生労働省の定義では、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態と謳っています。引きこもりの原因としてはいろいろあるでしょうが、訴えたいことが通らない、言えないなどがあるとも考えられます。しかし時間経過とともに、直接的原因だけではなくなってくる場合があります。治療には丁寧なカウンセリング等が必要です。
「パニック発作」
突然息苦しくなったり、呼吸が乱れたり、多量の汗をかいたり、めまいなどを引き起こす発作です。過呼吸になることもあります。電車に乗れなかったりする方もいます。広い場所や閉ざされた場所も苦手になることもあります。またパニック発作が起きないか不安という要因で発作を繰り返す場合もあります。呼吸を整えながら、少しずつ不安を安心感に変えるように対処しなければなりません。「パニック障害」という疾患で多く見られますが、予期不安の延長で他の疾患の方が起こる場合もあります。
「解離」
強いストレスなどにより、そこから逃げるため(守るため)に記憶喪失になったり、遠くへ逃げたり、別の人格を形成することもあります。自分が自分でないような感覚を生じることもあります。
「恐怖」と「依存」
対人恐怖や何度も手を洗う不潔恐怖が出る場合があります。逆に頼りすぎてしまう「依存」があります。ニコチン中毒、アルコール依存、薬物依存があります。また社会的なものとして「ギャンブル依存」「ネット依存」も多く知られています。この「恐怖」や「依存」が先にあり精神疾患になる場合もあります。「水中毒」という病気も統合失調症患者に多く見られます。精神疾患患者の特徴として「白黒はっきりさせる方が楽」というものがあり、「恐怖」のように避ける=排除するか、「依存」のように頼りすぎてしまう傾向があるようです。
今回、精神疾患に起こる症状を一部ですが書かせていただきました。一時的症状だけでは病気の特定は医師でも難しく、治療をしながら経過を観察する必要があります。自分が抱えている生きづらさ、生活や暮らしのしづらさがあれば医師へ相談しましょう。

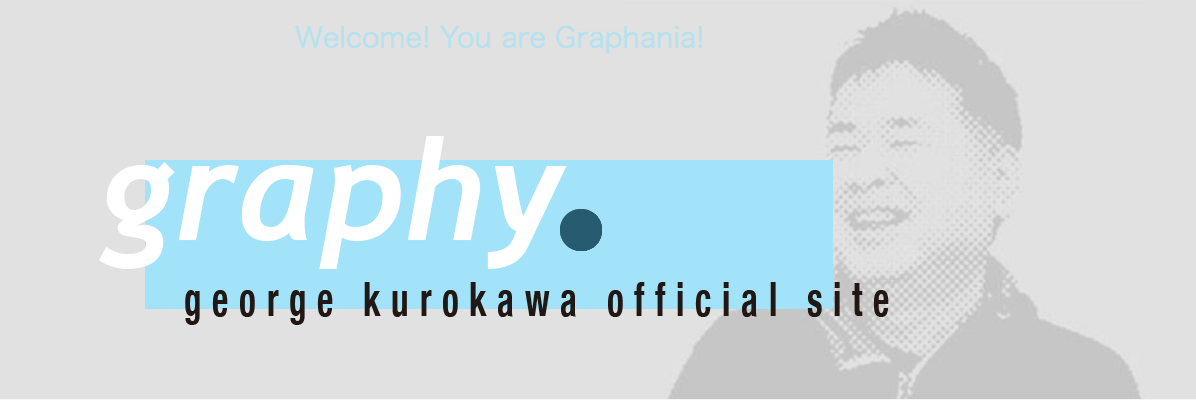

コメント