聞きたかったメンタルヘルスの話 vol.16
このコラムは筆者が以前某医療コラムで連載していた修正前の記事本文です。内容は作成当時のもので、現在は異なることもありますので、ご了承下さい。あくまでアーカイブとしてご覧ください。
以前のコラムで制度や法律の歴史を書きましたが、その中で日本では世界に比べて長期入院患者が非常に多くいます。厚生労働省の調べによると、近年の日本の精神病床数は35万床で、入院患者数は30万7千人(平成23年調べ)に及びます。このうち1年以上の入院患者数は20万人です。疾患別だと、統合失調症はその半数以上を占めます。世界的に見てもOECD諸国の中で日本は精神科の病床数や自殺率も突出しております。世界では当たり前の地域で医療を受けながら暮らすことが、日本ではまだまだ軽視されているのです。また驚くことに30年以上の入院患者が未だなお多数いるのです。当然のことながら半数以上は65歳以上の高齢者です。その多くは退院するとしても戻るところ、受け入れるところがない(居住や支援がない)「社会的入院」です。患者の家族が引き取りを拒否したり、病院自体が退院を視野に入れていない場合があります。長期入院患者を囲むことで、病院の大きい収益にもなっています。長期入院患者が退院できぬまま亡くなってしまう「死亡退院」は年間1万人を超えています。
では、その病棟はどうなっているのでしょうか。
病棟には閉鎖病棟もあります。施錠をされた病棟で、許可がなければ出入りができません。面会も限られてしまいます。外部との仕切りの窓は小さく、外の景色を眺める窓には鉄格子があるところもあります。食事は管理されたものが出され、食堂にはあらかじめ名前が記入された席があり、そこには「大盛」など記入されている場合があります。時間になれば配膳されますが、そこにあまり明るいコミュニケーションは感じられません。お風呂の時間も制限され、日中はフリースペースで数少ないテレビを共有したりします。入院患者数は自分が退院することすらイメージできず、人間としての当たり前の欲や希望が失われています。人権や人格も尊重されているとは言いにくい状態です。下手をすると、入院していた方が安心と信じ込んでしまっている方が多くいるのです。最近は病棟老朽化のため建て替える病院も多く、その際病床を減らしたり、入院患者の処遇を改善する病院も出てきていますが、昭和時代の刑務所のような印象を受ける病院も未だにあります。新築された綺麗な病棟でも「自分は退院できない。しない方がいい。」と感じている方が多くいます。充実したアメニティや時間で配膳される食事、体調を崩した時に医者がすぐそばにいるなどのことから、本人たちも入院を当たり前のように思っているのです。
それではどうすれば社会的入院の方々を地域で暮らせるように移行ができるか。
無論、病院は住むところではありません。そこで住居をどこにするかということもありますが、その前に本人たちに「支援があれば、地域で暮らせるんだよ。退院できるんだよ。」と気づかせる種を蒔かなければなりません。しかし、もっと啓発しなければいけないのは、病院側の医師、看護師ら、そして受ける地域側の認識です。一番退院できないと思っているかもしれません。そこでよく耳にするのは「何かあったらどうするんだ」という声ですが、何かあった時の専門職だと思うので、その人たちに「あなたたちは何のために勉強してきたの?」と言いたいくらいです。そんな当事者や医師、看護師、地域の担当者に訴えることができるのは実際に「退院して、地域で暮らしている」当事者たちの声です。まさにピアの力です。僕自身も地域移行のお手伝いをしていますが、入院した経験がないので、実際に退院した当事者の言葉を聞くと重みがあります。彼らの地域生活の楽しさ、自由さ、自分らしさを語ってもらうのが一番響きます。長期入院の患者さんにはじめ「退院したい?」と聞いても「退院したい!」とはなかなか言わないです。長期入院の間にそういう風に洗脳されてしまっているからです。しかし地域で暮らしている当事者を見て少しでも外に出たいと少しでも思っていただいた方に、一緒に外出同行をして、買い物をしたり、美味しいものを食べたりと体験していただき、少しずつ地域へ移行するのです。本人が「退院したい!」と思ったら退院支援が具体的に動き出します。
住むところはどうするのか。
みなさん、退院したら戻りたい場所というのがあります。生まれ育ったところや、入院前に住んでいたところなど。実家に帰りたいという方ももちろんいらっしゃいます。しかし、長期入院をされた方が望むところが昔とは変わっている可能性があります。家族の住むところでの生活が難しければ、グループホームなどの通過型もしくは滞在型の居住施設です。支援を受けながら地域で暮らすのです。訪問看護などの支援もあります。日中は生活訓練などの施設を利用できます。
僕がピア・スタッフをしていて病棟にお邪魔させていただく機会もあります。その時とてもか細く色白で弱々しく感じていても、地域へ移行したらとても健康的で表情豊かになられた方を見ています。やはり自分の住みたい地域で生活することはとても大事なんだと思います。ある当事者は言いました。「退院するためにグループホームを目指しました。グループホームに住みだしたら一人暮らしを目指すようになる。」まさに地域へ暮らすことを目指していくのです。
病院は住むところではありません。病院は病気を治すところです。治せないまま何十年も入院させているのはおかしいです。今は診療報酬の改定などがあり、入院を長期化させない制度になっています。また病棟の老朽化などを理由に建て替えをしているところが多くあります。そこで政策として病院が「病床転換型居住施設」を作ろうという動きが出ています。もう一度言います。「病院は住むところではありません。」これは地域移行ではありません。病院の新たな囲い込みに過ぎません。どこまで精神疾患患者の人権を奪うのかと思います。多くの団体が「病床転換型居住施設」に反対声明を出しています。受け皿が少ないのも事実ですが、病院に作るのは僕は反対です。社会的入院は精神保健に遅れた日本社会が産んだものですから、社会が受け皿を作っていくべきです。

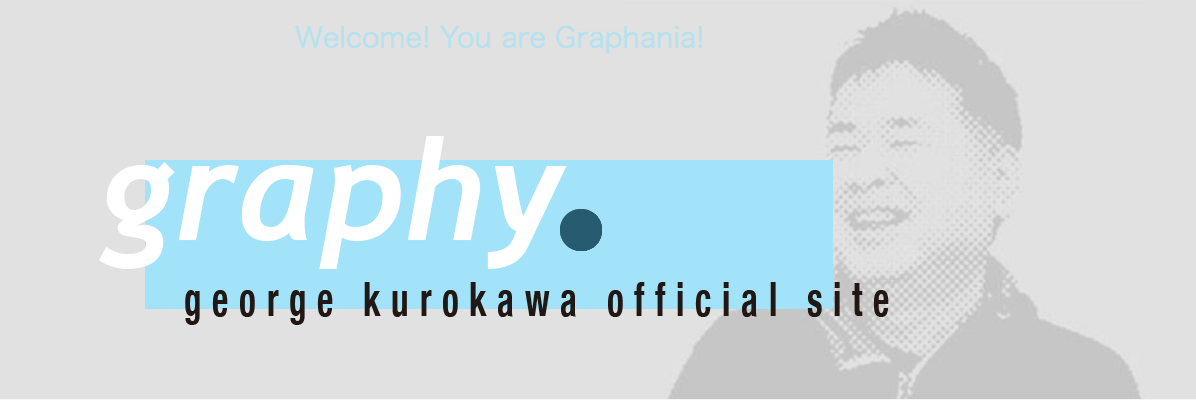

コメント