聞きたかったメンタルヘルスの話 vol.15
このコラムは筆者が以前某医療コラムで連載していた修正前の記事本文です。内容は作成当時のもので、現在は異なることもありますので、ご了承下さい。あくまでアーカイブとしてご覧ください。
10代20代前半というのは、人としても一番成長する年代ですし、自我や人格、性格なども形成される時期です。いろいろな人たちにも影響を受ける時期です。大人になる過程でのこころの成長、体の成長があり、そのスピードやバランスも不安定で「揺れる世代」「悩める世代」であります。そんな思春期のこころとメンタルヘルスについてお伝えしたいと思います。
身体の成長と変化
体格もどんどん成長する時期ですし、周りのみんなと比較することも多いです。自分の身体に起こる変化が恥ずかしくなることもあります。友人同士でオープンに話せればいいのですが、照れや恥ずかしさでその成長に戸惑い、悩みの一つでもあります。親子でお風呂に入っていた場合、思春期から一人で入るようになるタイミングでもあります。お風呂に一緒に入っている時に子供の身体の成長に気づいたら、自分の思春期の頃を思い出しながら、その変化について話をしてみてください。
性の目覚め
身体と心の成長により、異性や同性を「性」として意識が出てくる時期です。「好き」「憧れる」といった感情が生まれます。性機能も大人へと変わっていく時期ですので「性欲」もでてきます。周囲の成長と自分の成長の差が気になり出したりします。性の対象として人を好きになることに高揚感や罪悪感をいったりきたりもします。性の成長は心を揺らす一つでもあります。同性が気になることも異性が気になることもあります。異性に対し興味が深まることもあれば、同性を好きになるなどLGBT(セクシャル・マイノリティ)のことも無視はできません。学校でも「性教育」の授業はあると思いますが、家族でもしっかり見つめておき、話をすることが大事です。
こころの成長、自我の目覚め
家族という社会、学校という社会、子供同士の社会などでたくさんの人と出会いながら、自分の好み、興味、様々な価値、存在のあり方に気付きだし、周囲の人と比較しながら「自我」が形成されていきます。自然にできていた自我やその成長にに自分で戸惑うことですらあります。成長過程ではとても大事な時期であり、この時期は多くの体験とコミュニケーションが大事な時でもあります。
思春期の悩み
こころと身体の成長と、性の目覚めによりそれだけでも子供本人には悩みの種がいっぱいです。でもそれだけでなく、思春期はいろいろなことで悩まされます。まずは「進路」。勉強することですら戸惑いを感じる場合もありますが、自分のこれから「未来」についても不安になったりして悩める問題の一つです。「成績」も評価が得られないと悩みのタネになります。テストの結果に一喜一憂です。勉強だけでなく運動もです。スポーツが得意だと人気者になることは昔からありますが、その反対側に運動が苦手な子が居ます。苦手なことに関して自責の念を抱く子もいます。
そして「人間関係、いじめ」。友達との関係も悩みの種です。なかなか友達ができずに悩むこともあれば、学校での問題で不登校になるケースもあります。最近は友達のやり取りにSNSでの関係も増えていますから、子供の社会も複雑です。いじめに発展する場合もあります。いじめはいつ加害者側になるか被害者になるかもわからない深刻な問題です。大人が異変に早く気づく必要があります。
「恋愛」もこころを揺らします。好きになった人が自分を好きとは限りません。失恋のショックは大きいです。思いが成就していたとしても、交際する中で悩みはつきものです。
「悩みはがまんするしかないのかな?」http://psycience.com
こうした悩みから脱け出せず、苦しむ思春期の子たちがたくさんいます。そんな方のために東京大学や精神科医が中心となってできた中学校保健体育副読本「悩みはがまんするしかないのかな?」がダウウンロードできます。漫画で描かれていて、子供達自分で何ができるか分かりやすく書かれています。
「自殺」
悩みのその先に「自殺」という深刻な問題があります。若い頃はこころが1日の中でもかなり変わりますし、不安定です。若いので衝動性もあります。辛い気持ちと衝動性が加わると自殺の危険があります。また一人で悩み続けることも背景の一つです。笑顔で元気そうでいても、深い悩みを抱いていることがあります。15歳~19歳の死因1位は「不慮の事故・自殺」です。死因の3分の1を占めます。20代の死因1位は「自殺」です。こちらは死因の約半数です。(いずれも厚生労働省調べ)やはり異変に大人が早く気づき、悩みに寄り添うことが大事です。若者の自殺問題の解決に NPO法人Light Ring http://lightring.or.jpも取り組んでいます。代表の石井綾華さんは先ほどの「悩みはがまんするしかないのかな?」の制作にも参加されています。
「引きこもり」
いじめなどによる不登校などで引きこもりになる若者もいます。引きこもりの定義には状態によって違うので範囲が違ってくるのですが、内閣府の調査では広い意味での引きこもりは69万人以上いて、自分の部屋から出ない方は4.7万人いることがわかりました。その背景の学校生活において「我慢をすることが多かった」、「友達にいじめられた」、「いじめを見て見ぬふりをした」、「一人で遊んでいる方が楽しかった」、「学校の先生とうまくいかなかった」 が多かったとされています。家庭生活では「親が過保護であった」「我慢をすることが多かった」、「自分で決めて相談することはなかった」、「両親の関係がよく なかった」、「親は学校の成績を重視していた」、「親と自分の関係がよくなかった」、「将来の職業 などを親に決められた」が多く、「親とは何でも話すことができた」が少なかった。 「過保護」と「何でも話すことができなかった」ことなどからすると、コミュニケーションだったつもりがただの押しつけになっていた可能性が考えられます。本を読む、インターネットやゲームをして過ごすことが多いようなので、引きこもっている方には、手紙やSNSという手段も有効かもしれません。
「反抗期」
自我が出てくると、社会や大人たちともぶつかり出します。「言葉」をいろいろ覚え始め、主張や対抗する音葉を使い始めます。よくよく聴いていると、子供の方が正論を言っている場合もあります。大人の意見を押し付けるのではなく、聴く耳を持ちましょう。あー言えばこー言うのようなコミュニケーションがぎこちないこともありますが、大人になる大事な過程ですので、大きな器で受け止めましょう。自分の反抗期のことを思い出してみてください。むしろ反抗期がない方がメンタルヘルスでは危うくて、思いを内に秘めやすい傾向にもなるので「優等生」過ぎることにも気をつけてください。
思春期と精神疾患
こうした思春期のこころの揺れは思春期ならではのものでもあります。成長過程では当然誰でもありえます。しかし精神疾患と診断されるもこともあります。これは素人では判断できませんし、医療側も慎重になります。処方に関してもしかりです。大人になってから精神科にかかり「10代から発症していたであろう」と診断されるケースもあります。この問題に早期に対処するには、何度も言いますが周囲や大人が普段からコミュニケーションを持ち、サインを見逃さず、寄り添うことです。話を押し付けるのでなく、思いを聴く、思いを言える環境作りが必要なのです。若者専用の相談ダイヤルなどもありますので利用してみてください。(若ナビ http://www.wakanavi-tokyo.net)そして、精神状態が安定しない、希死念慮があるなどサインに気づいたら、医療とつながることです。

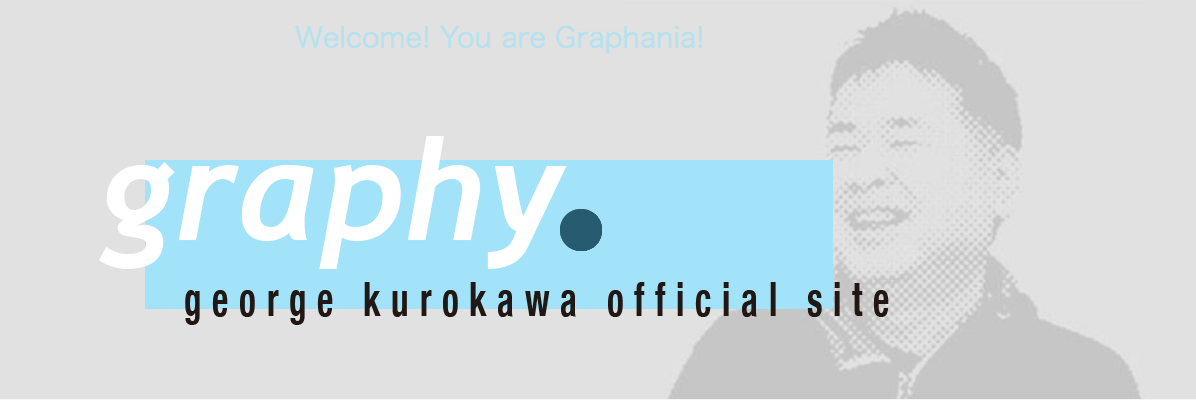

コメント