聞きたかったメンタルヘルスの話 vol.13
このコラムは筆者が以前某医療コラムで連載していた修正前の記事本文です。内容は作成当時のもので、現在は異なることもありますので、ご了承下さい。あくまでアーカイブとしてご覧ください。
この連載を始めてから、多くの患者さんからご意見をいただいています。その多くに支援者や医療従事者、制度への不満があります。このコラムでは今まで主に情報が行き届いていない方へと掲載をしていますが、精神疾患を囲む精神保健福祉の側面には行き届いていない背景があるようです。今回はその背景が生まれた歴史の話をしてみたいと思います。
昔、精神疾患に限らず、原因のわからない病気、難病、奇病と言われるものにかかった人は隔離されたり、村八分にされ、ひっそりとしか暮らせない時代が長くありました。座敷牢に監禁されることもあったそうです。そして明治時代、旧中村藩主・相馬誠胤が統合失調症を患ったことを発端に世間に物議を交わした「相馬事件」をきっかけに「精神病者監護法」が1900年に公布されます。「精神病者」という言われ方にも差別を感じるのだが、「監護法」という言葉にもびっくりです。「看護」ではなく、家族が監禁することを許可する法律なのです。病気を治すというより治安を守るという色の強い法律です。これが精神疾患患者に対する日本で初めての法律になる。精神科病院でも有名な東京都立松沢病院も元は東京府癲狂院(ていきょういん)という名でありました。
1914年には、精神疾患を治すことを少し考慮された「精神病院法」が公布されます。これは各都道府県が精神科病院を設置しようとするものです。しかしそれは患者を入院させる目的そのものでした。また全都道府県に公立精神科病院ができるのには時間がかかりました。
1950年、「精神衛生法」が施行され、精神病院法が廃止されます。精神衛生法は各都道府県に精神科病院の設置を義務付けしました。これもまた患者を入院させ隔離させる目的が濃いものです。監禁する場所が家から病院に変わったということです。この時に自傷他害の恐れのあるものに対して即時に強制的に入院させる「措置入院」の制度ができます。1960年からは医療金融公庫の設置により私立の精神科病院が大量にできることになます。
1964年、ライシャワー事件が起き、精神衛生法改正がされます。国会で「精神障害者を野放しにするな」のような発言が総理大臣から発せられたのです。そしてこの改正で自宅などにいる精神疾患患者をより管理する色合いが強く出ます。患者の医療を促進するために通院医療費を半分公費で負担する制度(32条)も始まります。(これがのちの自立支援医療費負担制度につながります。)ある調べによると当時精神疾患のおよそ半数が医療につながっていない状態だったとも言われています。またこの時保健所が地域の精神保健の中心的な役割を担います。
この「精神衛生法」あたりが入院・隔離が中心となった時代で、このころから入院された患者が長期に閉鎖病棟などに拘束されるようになり、本来は退院できるのに、社会制度が整備されていないため、現在も「長期入院患者」として病院で過ごさなければならない状態になっているのです。また世の中の風潮や、医療側の営利目的もあり、ベッド数以上の患者を入院させる病院も出てきてしまいます。残念なことに高度経済成長とともに、日本の精神科病院のベッド数は増え続けたのです。
1970年障害者基本法が施行されます。ただし、ここには精神疾患患者は含まれていません。
そして1983年「宇都宮事件」が起きます。精神疾患患者が犠牲になったのです。この事件をきっかけに精神疾患患者の「人権」が世に問われることになります。このことが世界的にも問題になり国を動かし、1987年「精神保健法」が成立します。ここでやっと「社会復帰」「人権尊重・権利擁護」「任意入院」などが盛り込まれます。作業所など社会復帰施設の規定もできることになります。
1991年、国連で「精神疾患を有する者の保護及びメンタルへルスケアの改善のための諸原則」が採択されます。
1993年には精神保健法にも入院という精神疾患患者を囲おうとする視点から、自立した地域社会生活を送れるような視点が出て精神保健法が改正されます。またこの年に障害者基本法で精神疾患も「障害者」として明確に位置付けられました。
1995年精神保健法が見直され「精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)」となる。ここでやっと「福祉」の視点が入ります。ここで社会復帰施設の役割として「生活訓練」や「住居」「授産」など明確になります。入院患者が地域生活に戻るために支援を受けながら自立した地域生活を訓練できる「グループホーム」の法制化もされました。この年の改定でようやく精神障害者にも「障害者手帳」が交付されるようになる。しかしこの頃には今のように写真添付ではありませんでした。
この後も精神保健福祉法は何度か見直しがされています。そんな中、飛び出したのはグランドデザインや障害者自立支援法です。障害者自立支援法は2005年の小泉内閣で閣議決定されました。その背景は保護から自立を目指すとは名ばかりで、少子高齢化による財源不足なのです。介護保険への画一化を狙ったものでもあります。福祉支援を福祉サービスとし、当事者の負担を増やす支援制度から受益者負担へ、応能負担から応益負担へと変えていくものでした。
これに関しては全国の当事者や家族、関係者の猛反発が起きました。そんな中2006年4月に法律の一部が、10月に完全に施行されました。当時、障害者福祉の現場では大混乱が起きました。2012年、野田内閣によりこの障害者自立支援法は廃止されました。その後、障害者支援法となり考え方は変えたようですが、法律の文章などはほぼそのままです。
2010年、ここで新たな動きが出ます。NHKの報道番組が内外の精神保健システムの取材をし報道したことに当時の長妻厚生労働大臣が関心を抱き、東京都立松沢病院の岡崎祐士院長(当時)に声がかり、「当事者家族のニーズに応えることを主軸に考え、現実の精神保健医療の諸問題を、早く、根本的に、大胆に改革する提言をまとめよう」という動きが始まり、「こころの健康政策構想会議」が結成されました。
ここには当事者、家族、支援者、医療従事者、研究職などが垣根を越えて手弁当で介し、「提言書」をまとめ上げました。これは国民誰もがこころの健康を大切にする権利が平等にあり、もしこころの健康が脅かされても安心して地域で暮らせる法律の提言書です。そしてこれを厚生労働大臣に提出しました。さらに構想会議の委員を中心に、精神保健医療改革を実現させ、「こころの健康保持および増進のための精神疾患対策基本法(仮称)」の制定を目指そうという意見が大きくなり、「こころの健康政策構想実現会議」を立ち上げることになりました。ここで100万人署名運動が起き、72万筆を集めました。しかし、この時には国会情勢が変わり、また日精協(日本精神科病院協会)などの外部圧力もあり、国会採択には至りませんでした。しかし、その後、当事者・家族が中心と なって専門職の人々と共同して取り組んできた提言の実現を求める運動は、379 の地方議会(人口カバー率82%)で意見書が採択され、1 億人近い住民の支持があることを物語っています。 そして現在、2013年より施行されている障害者総合支援法で精神保健福祉医療が動いています。対象範囲にやっと難病の方が含まれました。
(http://cocoroseisaku.org/index.html)
このように精神疾患患者に関わる法律や制度はネガティブな要素から生まれ改定を繰り返しています。「当事者のニーズが反映する」なんていうのは程遠いのです。変遷を見ると、当事者のことを考えた制度づくりは見られません。満足のいかない支援が多発するのは当然かもしれません。ただし、現代を生きる我らは現代の制度を利用せざるをえません。そこは隙間だらけです。問題が山積です。一番困っているところに支援が届かない制度が多数あります。いつでも後回しにされているのです。
また制度を管轄するところを超えた支援をしてくれる方は少ないです。窓口をたらい回しにされることもたくさんあります。支援者との相性が悪いと、支援を受けたくなくなることさえあります。
他にも福祉職の待遇が改善されていない問題もあります。福祉職、支援者の質を上げることだけでなく、その環境もよくする必要があるでしょう。
そんな中でも、積極的に「こんな状態はおかしい」と声をあげ、運動してきた方がたくさんいます。現代まで改善してきたのもそんな熱意のある方の賜物であったりします。今までご尽力された方、制度に振り回されていた方々の願いが反映される日がいち早く来ることを願います。
精神的苦痛を症状や社会的偏見だけでも苦痛を受けているのだから、支援ぐらいは心地よく受けたいものです。これから社会が精神疾患患者にも配慮されたものになることを願っています。
参考文献:e-らぽーる https://www.e-rapport.jp/law/welfare/02.html
我が国における精神障害者処遇の歴史的変遷 -法制度を中心に-
新潟青陵大学看護学科 藤野 ヤヨイ

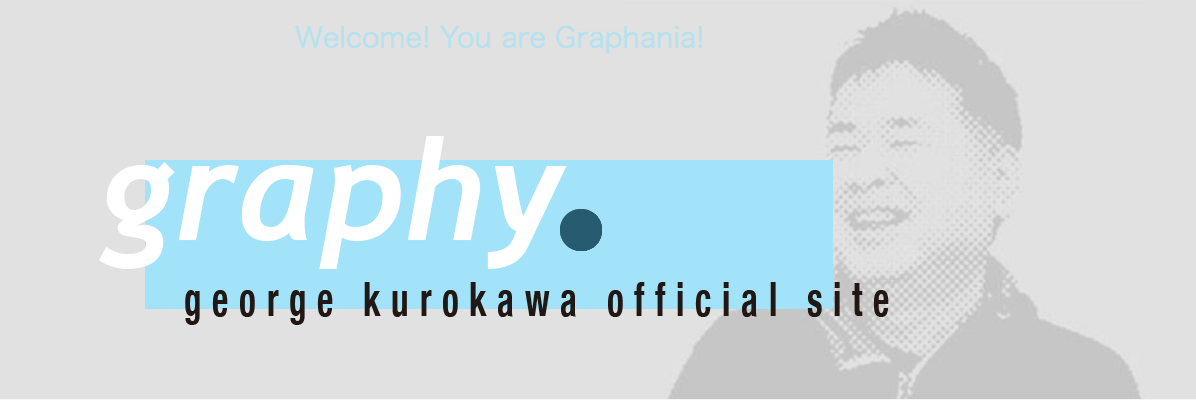

コメント